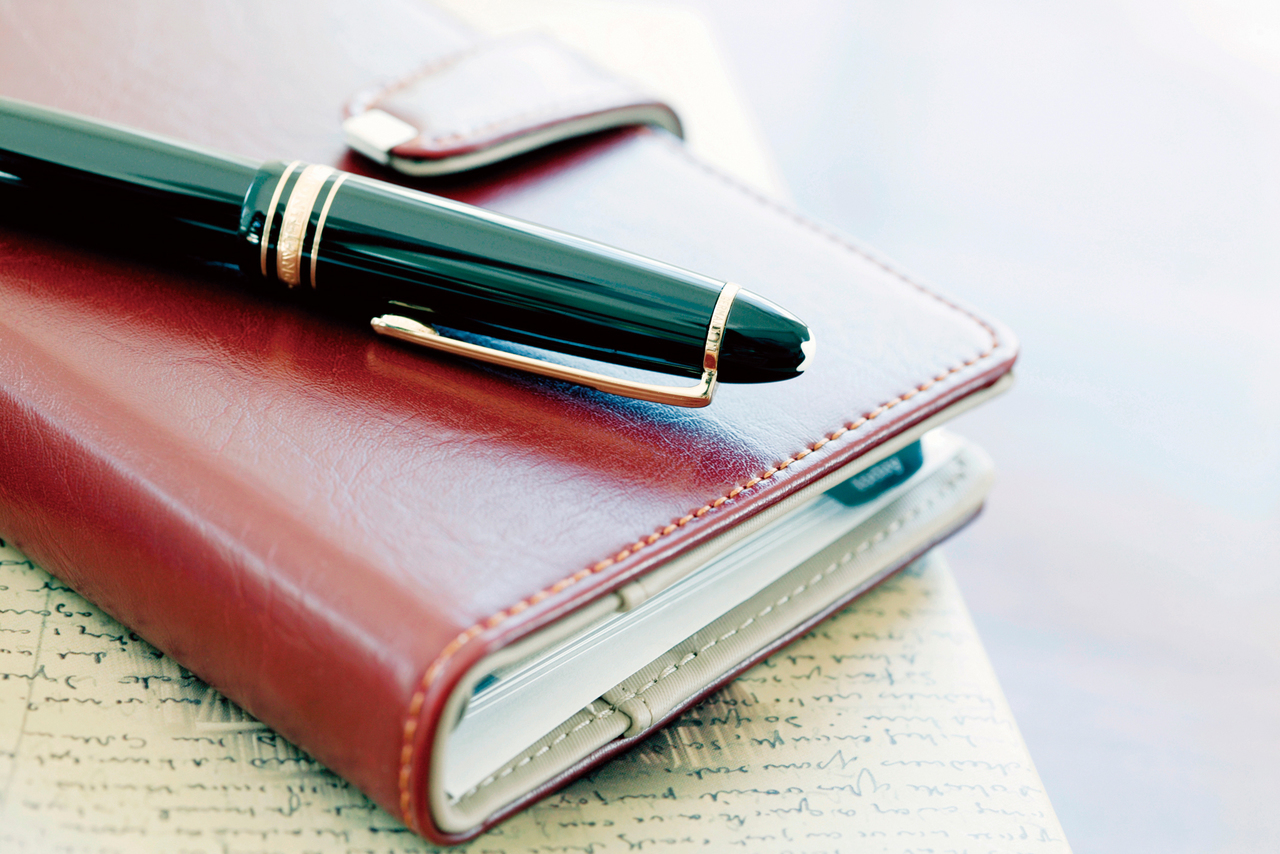〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
|---|
アクセス | 多摩センター駅徒歩3分 駐車場:近くに有料駐車場あり |
|---|
相続・遺言
相続・遺言でお悩みの方へ

- 遺言書が出てきたがどうしたらいいのか・・・
- 相続人の一人が使い込みや独り占めしようとしている・・・
- 自分には何も相続させない遺言書がある・・・
- 兄弟は生前援助してもらっていたのに不公平だ・・・
- 認知症だった親の遺言書があると兄弟が言っている
- 子ども達が揉めないように遺言書を残しておきたい
相続・遺言でお悩みの方は、多摩の弁護士、古林法律事務所にご相談下さい
相続は、突然、誰にでも起こりえる問題です。いざ相続となったとき、誰もが初めての経験ですので、 疑問や不安を抱えていることになります。 しかも、難解な法律用語に複雑な手続きが、 あなたの悩みを更に深いものにしてしまいます。 相続は一旦トラブルになってしまうと、 大切なご親族との関係が修復不可能なまでに悪化してしまい、 つらい思いをされることも多いのです。みなさんは、
私の家族は大丈夫!
と思っておられるかもしれません。 しかし、相続はほんの些細なことからトラブルになってしまうことが多いのです。 相続のトラブルの円満な解決のため、 まずは弁護士にご相談下さい。
また、ご自身が亡くなられた後に相続人の間で争いになることを望む方はおられないと思います。相続で争いにならないために、遺言は有効な手段になります。しかし、遺言も適切に残さなければ、争いを生んでしまいます。相続でトラブルにならないために、遺言作成について、まずは弁護士にご相談下さい。
相続調査(相続人や遺産の調査)ご相談ください

争いを未然に防ぎたい、相続の依頼をしようか迷っている、そんな方はまずは相続調査をご依頼ください。
相続でこんなお悩みありませんか?
遺言書作成
| 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|
| 基本コース | 11万円~ | 預貯金、有価証券、単純な不動産等を相続財産とする定型的な遺言書作成の場合です。 |
| 特別コース | 22万円~ | 特殊な財産や多額の財産がある場合や身分関係等について特殊な条項を加える場合など非定型的な遺言書作成の場合です。 |
| 公正証書遺言作成費用 | 5.5万円 | 遺言書を公正証書にて作成する場合の追加費用です。別途公証人役場への手数料がかかります。 |
| 相続人・相続財産調査費用 | 11万円 | 相続人が不明など身分関係の調査が必要な場合や相続財産の範囲が不明な場合など調査をするために追加で発生する費用です。 |
| 書類取り寄せ費用 | 1通5500円 | ご自身でお取り寄せされる場合には必要ありません。 |
遺言執行費用
| 遺産の額 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 33万円 |
| 300万円~3000万円までの場合 | 2.2%+26.4万円 |
| 3000万円~3億円までの場合 | 1.1%+59.4万円 |
| 3億円を超える場合 | 0.55%+224.4万円 |
- 特殊な事情や複雑な事情がある場合には、別途協議にて定めさせて頂きます。
- 遺言執行に際して裁判手続きを要する場合には、別途弁護士報酬を請求させて頂きます。
相続の弁護士費用
相続における弁護士費用は、相続調査+遺産分割事件(又は遺留分侵害額請求事件)の弁護士費用となります。相続調査から各事件に移行する際、各事件の弁護士費用を11万円を限度に割引させて頂きます。
相続調査を既にご自身でやっておられるケース等、相続調査が必要な程度に応じて各コースを選択したり、即遺産分割事件や遺留分侵害額請求事件としてご依頼頂けることもあります。まずは、ご相談下さい。
遺産分割事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 交渉(協議) | 22万円 | 経済的利益の額 |
| 調停・審判 | 33万円 |
※相続調査をご依頼頂いている場合は、上記着手金から11万円を限度に割引します
・交渉(協議)から移行する場合は、追加着手金22万円が発生します。調停から審判に移行する場合は、追加着手金は発生しません。
・使途不明金・預金引き出しについては、遺産分割協議・調停において合意が成立した場合には、返還が実現した額を経済的利益の額に加算して、報酬金を算定いたします。合意が成立せず、これらを請求していく場合には、不当利得返還請求(不法行為損害賠償請求)として、別途委任契約を締結頂き、着手金・報酬金を頂戴いたします。
・遺産分割の前提として、相続人の確定や遺産の範囲の確定などの確認訴訟を提起する必要がある場合には、着手金33万円、報酬金33万円を基本に、経済的利益が発生する場合には遺産分割事件の報酬金に準じた報酬金が発生します。
・調停の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回、審判の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回の日当が発生します。
・別途実費が発生します。
遺留分侵害額請求事件(請求する側)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 交渉(協議) | 22万円 | 経済的利益の額 |
| 調停 | 33万円 | |
| 訴訟 | 44万円 |
※相続調査をご依頼頂いている場合は、上記着手金から11万円を限度に割引します
・交渉(協議)から調停、調停から訴訟へ移行する場合、それぞれ追加着手金22万円が発生します。
・調停の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回、審判・訴訟の出廷 回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回の日当が発生します。
・別途実費が発生します。
遺留分侵害額請求事件(請求された側)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 交渉(協議) | 33万円 | 経済的利益の額 300万円以下 経済的利益の 27.5%(最低44万円) 300~1500万円 経済的利益の22%+16.5万円 1500万円~3000万円 経済的利益の16.5%+99万円 3000万円~3億円 経済的利益の11%+264万円 3億円以上 経済的利益の6.6%+1584万円 |
| 調停 | 44万円 | |
| 訴訟 | 55万円 |
※相続調査をご依頼頂いている場合は、上記着手金から11万円を限度に割引します
・交渉(協議)から調停、調停から訴訟へ移行する場合、それぞれ追加着手金22万円が発生します。
・調停の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回、審判・訴訟の出廷 回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回の日当が発生します。
・別途実費が発生します。
相続調査
相続調査をご依頼後、遺産分割事件や遺留分侵害額請求事件を引き続きご依頼頂く場合には、各事件の着手金を11万円を限度に割引いたします。
相続調査基本コース
相続調査の基本のコースになります。別途各種資料の取得実費がかかります。
料金
| 相続調査基本コース | 220,000円 |
|---|
- 相続人調査(戸籍謄本の取得)
※相続人は5名までとなります。6名以上は、追加料金(1名あたり1.1万円)が必要になります。 - 相続関係図作成
- 相続財産(遺産)調査
※金融機関及び証券会社は5つまでとなります。名寄帳は1つまでとなります。それ以上の調査は追加料金が必要になります。負債の場合は、3つまでとなり、それ以上は追加料金が必要です。(1社あたり1.1万円) - 相続財産(遺産)の評価額調査
※不動産は2社以上の不動産業者の査定を取得します。詳細な査定を取得する場合は、別途実費が発生します。 - 特別受益・寄与分の調査
※ヒアリングに基づいて、裁判例等から査定します。それ以外の調査については追加料金が必要になります。 - 遺産目録の作成
- 遺言書の調査
※公正証書遺言の有無を調査します。 - 遺留分侵害額の調査
- 解決方針のご提案
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
相続財産調査コース
相続財産調査に限定したコースです。相続人は資料などが揃っており、相続財産だけ調査したいという方向けのコースです。
料金
| 相続財産調査コース | 165,000円 |
|---|
- 相続財産(遺産)調査
- ※金融機関及び証券会社は5つまでとなります。名寄帳は1つまでとなります。それ以上の調査は追加料金が必要になります。負債の場合は、3つまでとなり、それ以上は追加料金が必要です。(1社あたり1.1万円)
- 相続財産(遺産)の評価額調査
- ※不動産は2社以上の不動産業者の査定を取得します。詳細な査定を取得する場合は、別途実費が発生します。
- 遺産目録の作成
- 遺言書の調査
- ※公正証書遺言の有無を調査します。
相続人調査コース
相続人調査に限定したコースです。相続財産については資料が揃っており、相続人だけしたいという方向けのコースです。
料金
| 相続人調査コース | 55,000円 |
|---|
- 相続人調査(戸籍謄本の取得)
- ※相続人は5名までとなります。6名以上は、追加料金(1名あたり1.1万円)が必要になります。
- 相続関係図作成
- 遺言書の調査
※公正証書遺言の有無を調査します。
目次
相続の基礎知識
相続に関する基礎的な知識の概要を紹介します。今後相続に関してより詳しい記事やコラムを掲載してまいります。
人が死亡したら、その人が有していた財産や借金、契約などはどうなるでしょうか?
そのまま放置することはできませんから、誰かに引き継がせる必要があります。
このような死亡した人の権利・義務を相続人に引き継がせることを、相続といいます。
被相続人は、死亡した人のことをいいます。
相続人は、死亡した人から相続する(権利・義務を引き継ぐ)人のことをいいます。
相続においては、相続人・被相続人という用語が頻繁に出てきます。逆に覚えてしまいそうな少しややこしい用語ですから、ここで確認をしてください。
法定相続人とは、相続人として、一定の割合で相続すると法律が定めている人のことをいいます。遺言がない場合もしくは遺産分割協議で合意しなければ、この法定相続人が、法定相続分で相続することになります。民法では、次のようなルールで法定相続人が定められています。
①配偶者は常に相続人になります
②血族は、次の順位に基づいて相続人になります。
同じ順位の人は、全員が相続人になります。先順位の人がいる場合は、後順位の人は相続人にはなりません。
第1順位:直系卑属(子ども、孫など)※子どもがいない場合は孫、孫がいない場合にはひ孫というように、次の世代が代わりに相続していくことになりますが、これを代襲相続といいます。
第2順位:直系尊属(親や祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹またはその子ども
配偶者や卑属など、その立場と構成によって相続する割合が定められており、この割合を法定相続分と言います。
具体的には次のようになります。なお、同一順位間で複数人いる場合には、原則として等分で分けます。
配偶者のみの場合 配偶者が全部
配偶者と第1順位の場合 配偶者1/2 卑属1/2
配偶者と第2順位の場合 配偶者2/3 尊属1/3
配偶者と第3順位の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺産の一定割合が保障されており、それを遺留分といいます。
遺留分は、法定相続分の2分の1となります。
ただし、直系尊属のみが相続人の場合には、3分の1となります。
相続人の中で、遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組・生計の資本として生前に贈与を受けた者がいる場合に、これら遺贈や生前贈与を特別受益として、遺産分割において考慮することになります。
具体的には、生前贈与を計算上相続財産に加え、みなし相続財産を算定します。(遺贈は相続財産なので更に加えることは不要です)
このみなし相続財産から、各相続人の相続分を計算します。
特別受益を受けた者は、この相続分から特別受益分を差し引いた残額が、特別受益を受けた者が受け取ることができる具体的相続分となります。
このような扱いを特別受益の持戻しといいます。
相続人の中で、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がいる場合に、遺産から寄与分を控除し各相続人の相続分を算定し、寄与をした者については寄与分額を加えて具体的相続分とすることになります。
なお、これまでは寄与分は相続人のみに認められてきましたが、民法改正により、相続人の親族であっても、無償で被相続人の療養監護等の労務の提供をしたことによって、被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した場合には、特別寄与料を請求することができることになりました。
原則として被相続人が死亡した時点で所有していた一切の権利義務のことをいいます。相続財産は、遺産と呼ばれることもあります。相続財産は、相続の対象となります。具体的には、現金や預貯金(債権)、株式、不動産、自動車、ゴルフ会員権など様々なものが相続財産となります。また、住宅ローンといった債務や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。
ただし、被相続人の一身に専属していたものは例外的に相続財産にはなりません。例えば扶養請求権などの身分上の権利や人格権といったようなものがあります。
相続が開始した場合、法定相続人は自分が相続をするかどうかに関して3つの選択肢があります。
相続においてはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、いわゆる借金も相続することになります。もし借金がある場合、相続人は常に相続しなければならないとすると、相続人にとっては不測の損害を被ることになりかねません。
そこで、単に相続するだけではなく、相続しない、全体でプラスなら相続するという選択肢が用意されています。
| 1.単純承認 | 相続人が被相続人の権利義務をすべて引き継ぐこと | ||
|---|---|---|---|
| 2.相続放棄 | 最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の権利義務を一切引き継がないこと | ||
| 3.限定承認 | 相続人が相続によって得たプラスの財産の限度でマイナスの財産(債務)を引き継ぐこと | ||
相続の開始を知ってから3ヵ月以内に限定承認、相続放棄の手続きをしない時や、相続人が被相続人の財産を消費したときも単純承認とみなされてしまいますから、注意が必要です。
遺言の基礎知識
遺言に関する基礎知識の概要をご紹介します。今後遺言についてより詳しい記事やコラムを掲載してまいります。
遺言とは、被相続人の最後の意思を表したものです。
一般的には「ゆいごん」と読みますが、法律用語としては「いごん」と読みます。もし弁護士など専門家にご相談される際に、「いごん」と聞いても驚かないでください。
遺言書は作成方法によって主に3種類あり、内容によってその効果が異なりますが、いずれの場合でも原則として法定相続分よりも優先されることになります。そのため、相続が発生した場合には、まずはこの遺言がないかどうか調べることが大切になります。
遺言書には、主に普通方式として3種類の方法があります。
それぞれにメリットデメリットがありますので、遺言の作成をご検討される際には、ご自身にもっとも適したものを選択されるのがよいでしょう。
| 自筆証書遺言 | 遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言のことを言います。ただし、財産目録はPCで作成したり通帳の写し等を添付することも認められます。 | ||
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 遺言者が、公証人に対して遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容を文書として作成するもの | ||
| 秘密証書遺言 | 遺言者が遺言内容を秘密にしたまま遺言書を封じ、公証人によって公証される方式の遺言 | ||
検認とは、家庭裁判所において、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名といった遺言書の内容について、はっきりとさせることをいいます。
遺言書が偽造されたり変造されたりしたものでないことを明らかにするための手続きです。したがって、検認によって遺言書の有効性や成立の真正が推定されるわけではありません。
公正証書および自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言以外の遺言書については、検認が必要となります。仮に検認をせずに勝手に開封したり執行を行った場合には、無効とはなりませんが、過料が科されます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実行する者のことをいいます。
遺言書で遺言執行者を指定することができます。また、遺言書で指定されていない場合にも、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができますが、遺言執行者を選任しなくてもよい場合もあります。
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に沿って相続することになります。
しかし、相続人全員が合意すれば、その内容とは異なる分割をすることもできます。
特に遺留分が侵害されているような遺言内容となっている場合に問題となります。
| 遺言能力 | 遺言当時、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足りる能力 |
|---|
簡単にいうと、遺言の内容や意味を理解できる能力ということになります。
遺言をするには、この遺言能力が必要とされます。
遺言能力の判断は、医学的判断を尊重しつつ、裁判所が法的判断を行うとされています。そして、法的判断においては、裁判所は統一的な基準を示していませんが、年齢や健康状態の推移、発病時と遺言時の時間的関係、遺言時及びその前後の言動、日頃の遺言の意向、遺言者と受贈者の関係、遺言の内容などを総合的に判断しているといっていいでしょう。
遺言者はご高齢の方が多く、認知症の場合は当然、高齢であればどうしても物忘れが多くなるなど遺言能力に疑義が生じやすいといえます。
また、遺言者の介護や身の回りの世話をした人など特定の人に遺言で多くの財産を残し、それ以外の相続人が遺言能力に疑義を抱きやすいという対立関係があります。
遺言を遺そうとお考えの方は、遺言能力が争いにならないように遺言作成時に医師の診断を受けたり、遺言書作成の様子を録画するなど工夫することが大切です。
弁護士による相続・遺言の法律解説
相続・遺言について、基本的知識より詳しい情報を知りたい方のための弁護士による相続・遺言の解説です。詳しい知識を身に着けることで、ご自身のお悩みの解決やご相談に役立ててください。今後も順次解説記事をアップしてまいります。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
古林法律事務所
住所
〒206-0033
東京都多摩市落合1-6-2
サンライズ増田ビル3B
アクセス
多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日